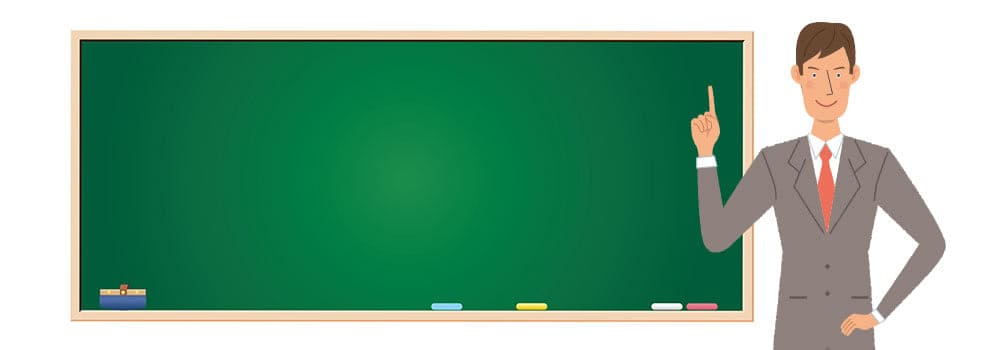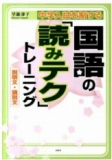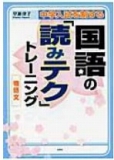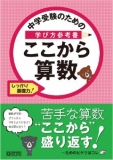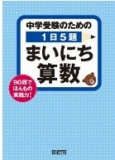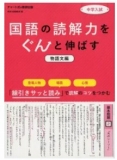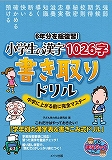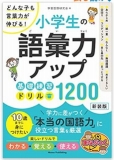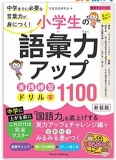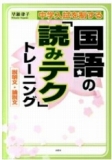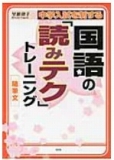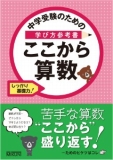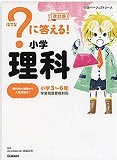具体的な数量が示されない問題は比で解く。
更新日:

算数の問題で、実際の数量や距離、速さなどが与えられていないタイプの問題がある。
こういう問題は、算数が苦手な子どもにとっては、チンプンカンプンでフリーズしかねない問題だ。
例えばこんな感じの問題だ。
【問題1】
駅まで歩いていくと20分、走っていくと12分かかります。
8時ちょうどに家を出て初めの6分だけ走って残りを歩きました。
何時何分に駅に着きますか。
この問題の場合、家から駅までの距離も歩く速さも不明(与えられていない)から、何から始めるべきか分からずに困ってしまう子どもも多い。
基礎学力アップに
スポンサードリンク(楽天ブックス 広告)
距離を勝手に決めて解く方法
こういう場合、2つの解放がある。
一つは「駅までの距離を勝手に決める」という方法で、たとえば20と12の最小公倍数の<60>を距離として解いてみる。
距離を60とすれば、走る速さは60÷12=5となり、歩く速さは60÷20=3となるので、6分間走ると30進むことになる。
残りは60-30=30になるので、歩く速さ3で割ると、残りにかかった時間が30÷3=10とわかる。
初めに6分走っているので、駅につくのは6+10=16分後で8時16分に駅に着くとわかる。
この場合、駅までの距離を「1」に決めても普通に計算できる。
距離を「1」とした場合、走る速さは「1/12」で歩く速さは「1/20」となり、計算が分数になるのだが、分数の計算を苦手としていない子どもにとっては、別に難しい解法ではない。
全体を最小公倍数に決めてみるとか、「1」にしてみるというのは、仕事算でも出てきた方法だが、こういう方法に馴染めるかどうかは、子ども次第なので、どちらにしろと押し付けるのは禁物だ。
ただ最小公倍数に決めるのにはコツが要る場合もあるので、とりあえず「1」に決めることにしても良いが。
6年生の夏以降の家庭学習ミニ模試に
入試本番に向けて週に数回、短めの物語文と説明文、計算と一行問題(標準編)などを2周以上行い、問題があれば「文章題に強くなる」の単元で復習。それができたら発展編へ進むと良い。短めの問題だと子供も取り組みやすい。
楽天ブックス(広告)
速さの比で解く方法
もう一つは速さの比で解く方法で、まず最初に歩く速さと走る速さの比を求める。
速さの比は、同じ距離を進むのにかかった時間の逆比(ぎゃくひ)になるので、この問題の場合、20;12の逆比の3:5になる。
ここで、歩く速さを分速③、走る速さを分速⑤、と決めることができて、そうすると歩いて20分かかる距離は(60)と決めることができる。
速さの比で距離を決める
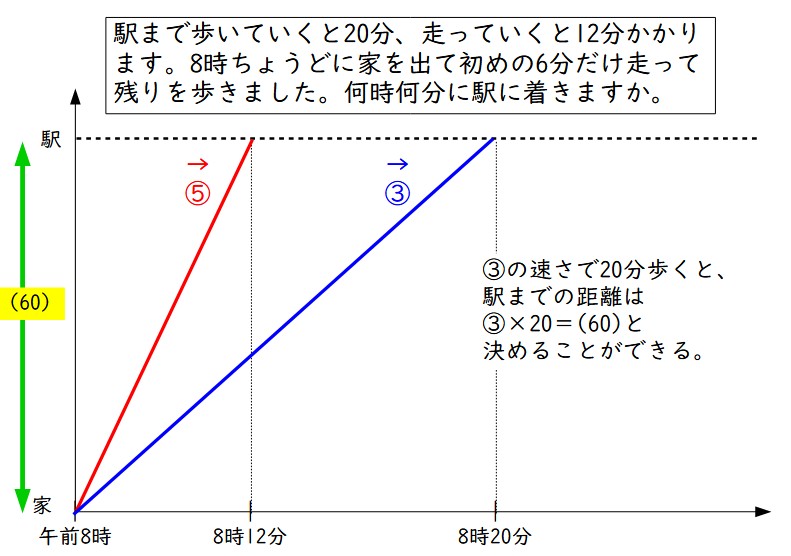
駅までの距離を(60)にするというのは、駅までの距離を最小公倍数で決めた場合と同じになっているが、距離を勝手に決めるということができない子供の場合は、速さから距離を決める方法のほうがしっくりする。
数学では、適当に「仮の値」を使うことが多いが、子どもによっては「勝手にそんなことしていいの?」と考えたり、「でも仮の値っていくつにすればよいの?」と迷ったりする。
だから速さから距離を決めるこっちの方法は、そういう子どもには適しているかもしれない。