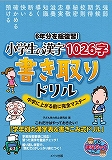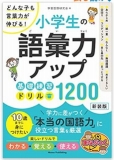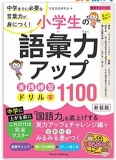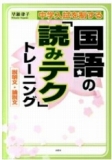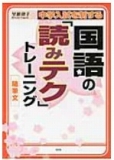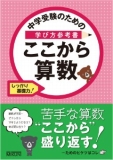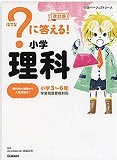熟語や語彙力を養ったあと、どうする?
更新日:

国語の勉強法の順序としては、まず漢字や語彙力の養成だ。
問題文に書かれている漢字や語彙の意味が全くわからなければ、それから先へは進めない。
そして次にやるべきことは、文章をたくさん読むことだ。
学んだ漢字・語句や語彙力を、実際の文章の中で発見して、学びを定着させる。
これは一文一文の意味をしっかり理解することが目的で、「精読」だ。
その文が何を表しているのかを、ちゃんと理解できてこそ、読解問題を解くことができる。
ところが実は、それだけでは中学入試の国語で合格点が取れるようにはならない。
なぜなら問題文を一文ずつ精読していたら、問題を解くスピードが遅くなってしまって、最後の問題にたどり着いたときには、試験時間がもう残ってないという状態になるからだ。
基礎学力アップに
スポンサードリンク(楽天ブックス 広告)
算数の解き方と国語の解き方の違い
算数の入試問題の場合は、計算問題や一行問題は最初の方に載せられているので、最初から解いていけばよい。
特に最後の方の問題は点数差をつけるような難しい問題が並んでいるので、時間が足りなくて手がつけられなくても支障はない。
計算問題と一行問題パート、そして残りの大問の1番だけ答えられれば、合格点が取れるように構成されている。
しかも問題が多岐にわたって、それぞれが独立しているから、解けそうな問題だけ解いて合格点を作れば良い。
だが国語の場合は、問題文をまず読むというところから始まる。
なのでそこで時間を食ってしまうと、問題を解く以前に終わってしまう。
問題文を読むスピードが遅いと、設問を読む頃には試験時間が尽きて、答えが書けなくなってしまうのだ。
中学入試の国語問題は、特に長い文章が多いから、まずその長文を「速く読む」ということが重要になるってことだ。
そして国語で点数が取れない子供の場合、話の根幹部分と枝葉の部分の区別がつかず、変なところで引っかかって時間を食う。
その結果、2つある問題文の後の方の問題の読解に手が回らず、最後の大問に1問も答えられずに0点になってしまう。
6年生の夏以降の家庭学習ミニ模試に
入試本番に向けて週に数回、短めの物語文と説明文、計算と一行問題(標準編)などを2周以上行い、問題があれば「文章題に強くなる」の単元で復習。それができたら発展編へ進むと良い。短めの問題だと子供も取り組みやすい。
楽天ブックス(広告)
要約力を養う重要性
国語で試験時間が足りなくなってしまうと、どうしようもない。
算数みたいに、解けそうな問題だけ選んで解くということができないので、問題文をさっさと読めないと、答えを書く前に時間が尽きてしまう。
原因ははっきりわかっていて、文章を読む速度が遅いことだ。
文章を速く読むことを「速読」と言って、速読の達人は、一冊の本をわずか数分で読んでしまったりする。
しかし国語の入試では、速読というほど速く読む必要はない。
必要なのは問題文の要点を素早く読み取ることで、あとは問題を解くために関係がある部分のみ精読するようにすれば良いだけの話だ。
ところが実は、これが子どもには難しい。
これができる子どもが国語で点数を取れる子どもで、偏差値が40前後の子どもはこれができない。
文章の枝葉の部分に引っかかってしまって、あらすじだけを追うということができない。
塾の生徒に問題文だけ読ませて、「何が書いてあった?」と尋ねても、何も答えられない。
生徒にしてみたら、そんなこと尋ねられたって、いろいろなことが書いてあって、何を答えればよいのか迷っちゃうってことなんだろう。
となるともう要約力を養って、どんどん読み飛ばせるように練習するしかない。
要約力のための問題集 通販
要約の特訓 上 新装版
要約力の基礎の基礎の問題集。これは京都の学習塾の先生が作った問題集で、穴埋め式。
入門編の「上」は短めの文章から、「いつ」「どこで」「誰が」「どうした」を抜き出す。
要約の特訓 中 新装版
上中下の3冊構成の中編は、上編の2倍以上の長さの文章を要約するのだが、中学受験を意識しているのか、地理や歴史の文章を短く要約する問題が多い。
要約の特訓 下 実践編
ふくしま式「本当の要約力」が身につく問題集
こちらは要約の方法を説明したあと、練習問題をやるタイプの問題集。
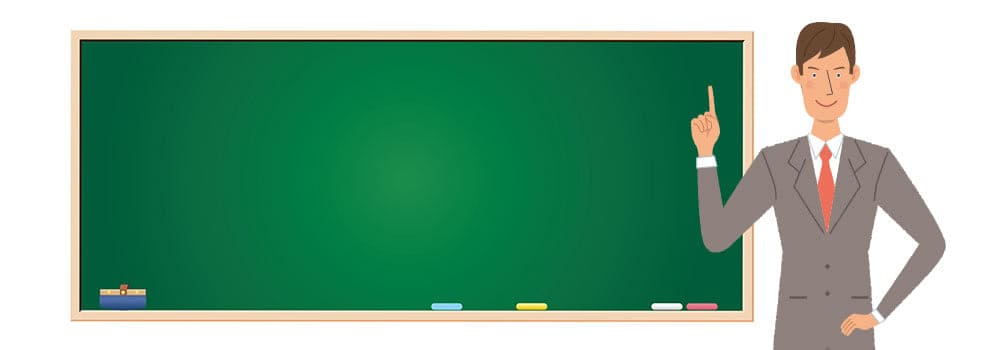
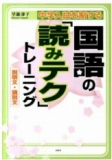
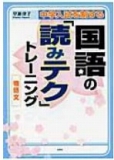
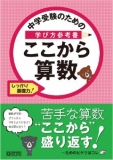
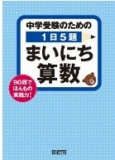


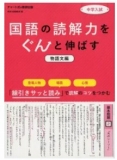







![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01f29dc3.1d043294.04d90740.56c8ea56/?me_id=1213310&item_id=21563227&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2273%2F9784867122273_1_4.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01f29dc3.1d043294.04d90740.56c8ea56/?me_id=1213310&item_id=21394391&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2280%2F9784867122280_1_4.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01f29dc3.1d043294.04d90740.56c8ea56/?me_id=1213310&item_id=21462784&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2372%2F9784867122372_1_4.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01f29dc3.1d043294.04d90740.56c8ea56/?me_id=1213310&item_id=21078480&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4214%2F9784804764214_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)