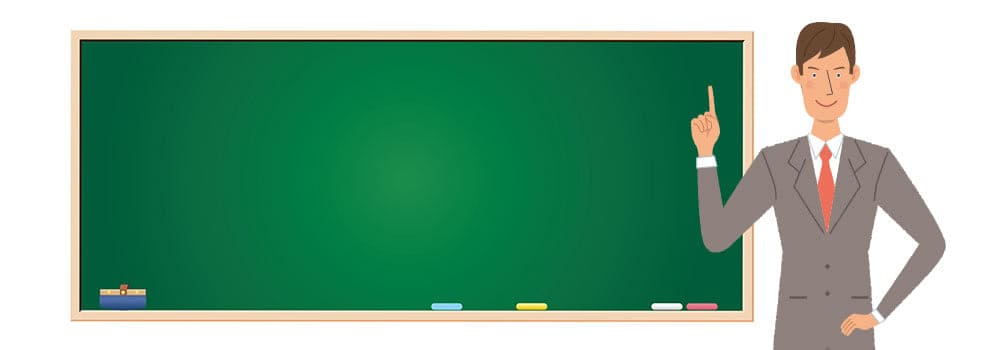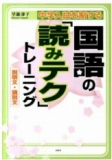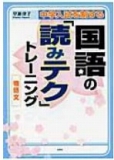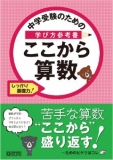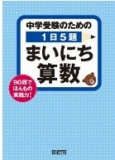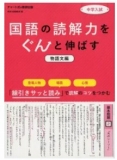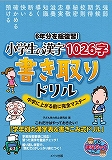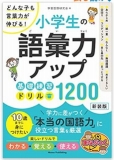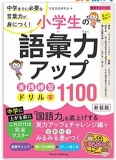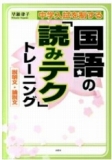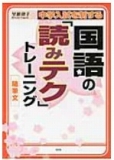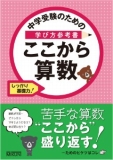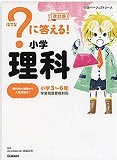日能研のカリキュラムは、途中入塾を考えたカリキュラム
更新日:

日能研のテキストは一般販売されていないし、塾でも注文できないから使えないが、どういうカリキュラムなのかは確認しておこう。
日能研のオープン模試(全国公開模試)では、試験範囲を公表していないので、全国公開模試を受験する際には試験範囲として参考にしたいしね。
日能研では、4年生の秋から中学受験のための学習が始まり、これを「系統学習」と呼ぶそうだ。
4年生の9月からスタートし、5年生の7月で学習が終わり、夏休みは復習と応用の演習を中心に行う。
こういう学習カリキュラムは、学年の途中から生徒を受け入れるのが容易だ。
たとえば5年生の夏前から中学受験を志したとしても、夏休み中にキャッチアップ授業を行って、必要最小限の知識を学習させて、塾に通わせることが出来る。
日能研の学習スタイルは、4週連続で計算なら計算、図形なら図形ばかりを学習するスタイルなので、授業と並行して未習の単元を学習していけば、どこかで追いつけるしね。
ちなみに昔は中学受験の勉強というと、5年生スタートが当たり前だったし、今でも5年生から中学受験の勉強を始めるお子さんも多い。
そういったお子さんは、四谷大塚やサピックスの半年以上進んだカリキュラムについて行くのは難しいが、日能研のスケジュールだと可能になるので、生徒を集めるために、こういうカリキュラムになっていったのだと考えられる。
基礎学力アップに
スポンサードリンク(楽天ブックス 広告)
日能研 5年 算数のカリキュラム 2月-7月
日能研のカリキュラムでは、9月の授業が第1回となっていて、7月の第38回までが一つの大きな区切りとなっている。
| 授業回(4年生秋からの通し番号) | 単元名 | 学習内容 |
|---|---|---|
| 第19回(4年生2月) | 整数の性質① | 約数と公約数 |
| 第20回 | 整数の性質② | 倍数と公倍数 |
| 第21回 | 小数の計算 | 小数の計算・逆算 |
| 第22回 | 分数の性質 | 約分と倍分 |
| 第23回(4年生3月) | 分数の計算① | 足し算引き算 |
| 第24回 | 分数の計算② | かけ算と1あたりの量 |
| 第25回 | 分数の計算③ | わり算 |
| 春期講習 | 復習と応用 | |
| 第26回(5年生4月) | 分数の計算④ | 四則混合計算・逆算 |
6年生の夏以降の家庭学習ミニ模試に
入試本番に向けて週に数回、短めの物語文と説明文、計算と一行問題(標準編)などを2周以上行い、問題があれば「文章題に強くなる」の単元で復習。それができたら発展編へ進むと良い。短めの問題だと子供も取り組みやすい。
楽天ブックス(広告)
5年生になる前の2月から新学年の4月までは、小数と分数に関係する授業が並んでいる。
そして5年生の4月からは図形(おうぎ形・多角形・図形を動かす)等といった単元を学習し、その後に面積図をちらっとやってから、線分図や割合を学習するというカリキュラムだ。
| 授業回(4年生秋からの通し番号) | 単元名 | 学習内容 |
|---|---|---|
| 第27回 | 図形① | 多角形の面積 |
| 第28回 | 図形② | 円とおうぎ形 |
| 第29回 | 図形③ | 複合図形の面積 |
| 第30回 | 図形④ | 図形のいろいろな性質 |
| 第31回 | 図形⑤ | 図形を動かす |
| 第32回 | 面積図のしくみ | 平均・つるかめ算 |
| 第33回 | 線分図と式 | 消去算 |
| 第34回 | 1あたりの差と全体の差 | 差集め算、過不足算 |
| 第35回 | 割合① | 割合の意味 |
| 第36回 | 割合② | 割合と線分図① 割合の三用法 |
| 第37回 | 割合③ | 割合と線分図② 相当算 |
| 第38回 | 割合④ | 売買と割合 売買算 |
| 夏期講習 | 復習と応用 |