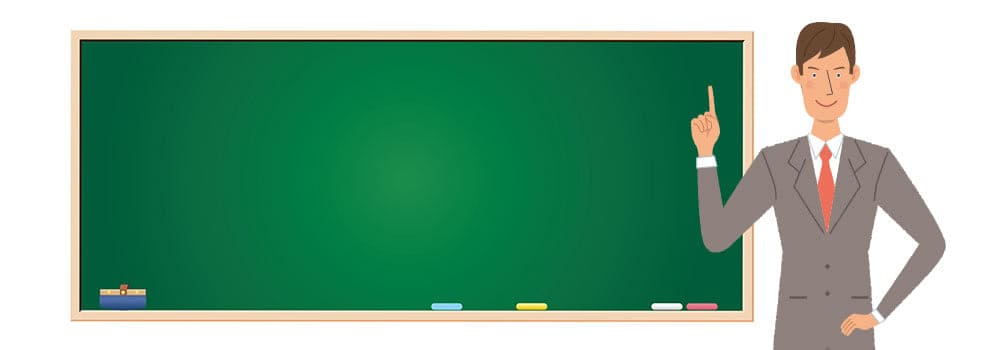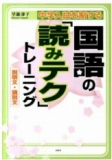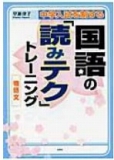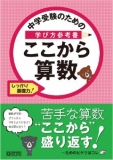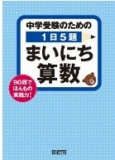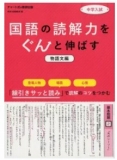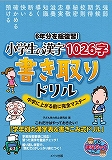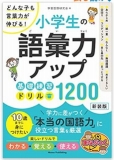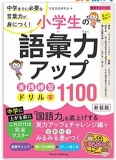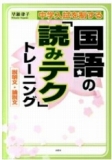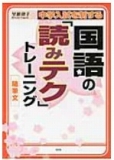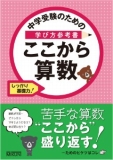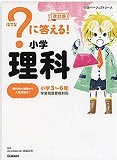夏休みに学習が終われば良い
更新日:

ここまで、予習シリーズや新演習(栄光ゼミナール)、日能研などの算数のカリキュラムを見てきたが、結論として中学受験の学習カリキュラムは、6年生の夏休み頃までに一通り学習できておれば良い。
もちろん夏休み前の7月に終わっておれば、夏休みからは入試本番に向けた形式で学習を進めることができるわけだが、お盆休み前に終わっておれば問題ないし、最悪8月末までに終わっておれば良い。
これは中学受験の勉強を始めた時期にもよるし、生徒一人ひとりの習熟度・習熟ペースにもよる。
そもそも子供の場合は、ロバスト性といって、学んだからと言ってできるようになるわけではない。
脳がまだ大人の脳になる途中なので、ある一定の年齢を過ぎないと、いくら頑張ってもできるようになるわけではない。
なので必ずしも受験塾のカリキュラムをしっかりこなしてなくて、塾の進度に追いつけていなくても、受験には問題ない。
変な話、6年生の冬休み前の12月あたりに突然、文字がきれいになって、覚醒する子どももいたりするので、入試が終わるまで根気よく勉強を続けることができるなら、それで良い。
ゴールは、目指す中学への合格であって、塾内で良い成績を取ることではないってことは、肝に銘じた方が良い。
それに、夏休みにしっかりと日に当たり、風邪を引きにくい身体を作るほうが、よっぽど受験には役立つ。
基礎学力アップに
スポンサードリンク(楽天ブックス 広告)
夏休み以降はアウトプット中心。アラカルト問題 一行問題を中心にやる
学習塾では、夏休みまでは、特定の狭い範囲の学習内容を教えて練習させる。
たとえば「速さ」の問題であれば、出会い算だとか、通過算だとか、旅人算だとか、時計算だとか、色々あるわけだが、そのうちの一つだけを集中的に学習する。
そして塾内テストも塾外テストも限られた範囲で出題されて、それで「よくできた」「できなかった」というふうに判断される。
しかし秋以降の模試も本番の入試も、そういう限られた範囲で出題されるわけではない。
計算問題は色んなタイプの計算問題が1つずつしゅつだいされるし、文章題も広い範囲から一題ずつ出題される。
難関校以外の中学では、この計算問題ブロックと一行文章題問題ブロックだけで、50点くらいの配点になっていて、ここをまずしっかり正答できることが、合格への第一歩になる。
なので6年生の夏休み以降は、今まで学習した内容を「思い出す」形で学習を進めることになる。
夏休み以前が「インプット中心」であったのに対し、夏休み以降は「アウトプット中心」になるわけだ。
そのために欠かせないのが、日能研ブックスの「計算と熟語」や、みくに出版の「まいにち算数」、「算数計算と一行問題」だ。
これらの問題集は一長一短があるし、子どもの習熟度合いによっては、まだ早い場合もあるので、どれをどの順番でやれば良いとは言えないのだが、計算と熟語の5年生版くらいから始めると良い。
ただ計算と熟語は図形問題が載ってないので、他の問題集も使う方が良い。
6年生の夏以降の家庭学習ミニ模試に
入試本番に向けて週に数回、短めの物語文と説明文、計算と一行問題(標準編)などを2周以上行い、問題があれば「文章題に強くなる」の単元で復習。それができたら発展編へ進むと良い。短めの問題だと子供も取り組みやすい。
楽天ブックス(広告)