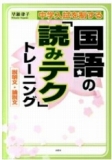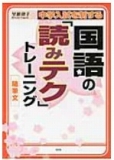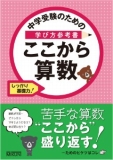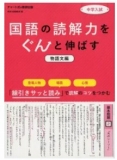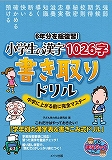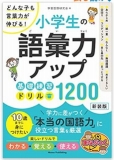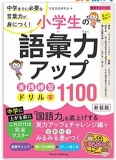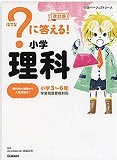算数のコツ 計算は、公式の下にまっすぐ書いてやる。単位も書く。
更新日:
それから、計算は基本的に、下の段に書いていく。横に書かない方が間違いが少ない。
もちろん、横にやっていった方が良い計算もあるが、たいていの場合は下の段に書いていった方が、間違えにくい。
たとえば、分母の異なる分数の足し算。
通分を右に書くと、混乱する子どもがいるが、下に書くと間違えが減る。
算数や理科のノートは、方眼になった方眼ノートを使った方が、タテヨコを意識しやすくなるので、オススメだ。
で、公式などがある場合も同様に、一番上に公式を書く。
そして上の図と同様に下の段に、具体的な数を描いていく。
なるべく真下に、できれば単位も添えて書く。
子どもにも二種類あって、
- 単位がなくても計算できる子ども
- 単位があった方が理解しやすい子ども
がいる。
単位を書く子どもは、単位があると、具体的なイメージが持てるのだろう。
複雑な問題でも、細かくやることを分割し、出した答えの単位がハッキリしてるから、よくできる。
数学などは、上に上がるに連れて抽象度がドンドン増していくから、具体的なイメージがないとついていけなくなる。
私もそちらの口で、単位を書かないと気が済まない口だ。
私の場合は、物理の勉強などをしていたときに、これがしっかり身に付いた。
基礎学力アップに
スポンサードリンク(楽天ブックス 広告)
物理の計算では、次元解析という検算方法がある。
それぞれの計算結果に必ず単位をつけていって、最後の答えの単位が求める答えの単位であれば、計算経過はとりあえずOK。
しかし単位が崩れると、明らかに間違っているとわかるわけだ。
やっていると何が何だかわからなくなってくので、単位を必ず書くようになったのかも知れないが、とにかく単位はできるだけ書くようにする。
しかし残念ながら、割合や濃度、比などは単位がない値であるから、この方法での理解は難しい。
単位を意識せずに計算する子どもの中には、こういう計算が得意な子どもがいるので、単位を書かずに計算することが一概に悪いとは言えないが、普通は単位を書かせた方が良いだろう。
6年生の夏以降の家庭学習ミニ模試に
入試本番に向けて週に数回、短めの物語文と説明文、計算と一行問題(標準編)などを2周以上行い、問題があれば「文章題に強くなる」の単元で復習。それができたら発展編へ進むと良い。短めの問題だと子供も取り組みやすい。