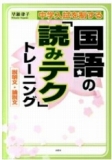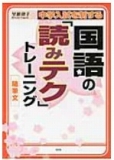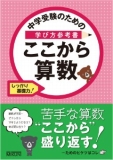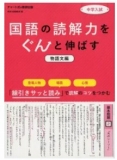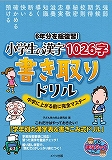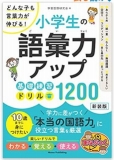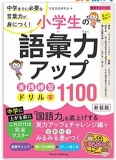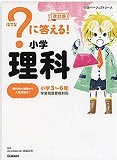勉強が出来るのには、段階がある。
更新日:

中学受験の勉強を毎日指導していても、殆ど成績が上がらない生徒も多い。
これだけやっているのに、なぜできるようになら無いのか、非常に不思議な子供も多い。
そう言う子供の場合、自分の好きな事だけやっていて、家庭で手伝いや雑用など、全くやっていなかったりする。
中学受験で良い私学に進学した中高生でも、学校で成績が最下位を彷徨っているような場合もそれが原因のことが多い。
中学受験の時に、毎日毎日散々勉強していたはずなのに、「何故こんな簡単なことができない?」と不思議に思う。
基礎学力アップに
スポンサードリンク(楽天ブックス 広告)
家で勉強も雑用もできない子供は、落ちこぼれる
中学受験のあと、成績が伸びなくなる子供の場合、小学生時代の家での行動に大きな問題がある。
学校で成績が低迷して、個別指導塾の門を叩いた生徒に尋ねてみると、「家では全然勉強してこなかった」と答えられ、唖然とした経験が私にもある。
中学受験の時に、毎日塾で散々勉強していたので、「家では勉強しなくて良いよ」「お手伝いもしなくて良い」と母親に言われ、その通りに家では勉強も手伝いもしなかった。
しようとしても、母親に「そんなことしなくてよい」と止められたらしい。
その結果、中学に進学した後も家で勉強する習慣がなく、また家庭の手伝いや雑用もせずに成長したのだという。
中学受験した生徒によくある「あるある」の一つだが、これは本当に重症で厄介で、成績はなかなか上げられない。
理由は簡単で、「具体的操作の経験値が低すぎる」からだ。
「実際にモノを動かして整理したり、工作したり、パズルを解いたり」という具体的な経験が足りないために、先に進めない状態になっているんだね。
6年生の夏以降の家庭学習ミニ模試に
入試本番に向けて週に数回、短めの物語文と説明文、計算と一行問題(標準編)などを2周以上行い、問題があれば「文章題に強くなる」の単元で復習。それができたら発展編へ進むと良い。短めの問題だと子供も取り組みやすい。
楽天ブックス(広告)
具体的操作と形式的操作
スイス出身の心理学者ジャン・ピアジェによると、子供の知的成長には4つの段階があるという。
その四つの段階と対応年齢は、次のようなモノだ。
ピアジェの4つの発達段階。
- 感覚運動期(0歳から2歳くらい)
- 前操作期(2歳くらいから7歳くらい)
- 具体的操作(7歳くらいから11歳くらい)
- 形式的操作(11歳くらいから)
この四つの段階は、順番に進むもので、早く進む子供もいれば、発達が遅れる子供もいる。
中学受験や、その後の勉強で問題になるのが、11歳までの「具体的操作」とそのあとの「抽象的操作」だ。
具体的操作や抽象的操作が何なのか、簡単に説明すると、
- 具体的操作 → 実際にモノを色々動かして考える。
- 抽象的操作 → 実際にはモノを動かさず、頭の中で考える
ということになる。
たとえば、算盤の上級者は、算盤を使わなくても難しい計算が暗算で出来る。
何故出来るのかというと、頭の中に算盤が置いてあって、それを頭の中で弾いて計算するからだという。
では実物の算盤を触ったこともない人が、同じようなことが出来るようになるかというと難しい。
そもそも算盤という概念自体が、頭の中にないわけで、そこから創っていかねばならない。
算盤で指を動かして、何万回・何十万回と計算することによって、ようやく頭の中に算盤という概念ができあがるわけだ。
この概念を「シェマ」と呼ぶ。
ピアジェの「シェマ」とは
シェマは「心象」や「概念」のことで、フランス語だ。
英語では「スキーマ」(schema)、ドイツ語では「シェーマ」と言うが、「大まかな図式・概念」のことだという。
新たなビジネスを始めるようなときには、スキーマやスキームという言葉がよく使われるね。
ただピアジェはこのシェマという言葉を、「自分なりの概念」という意味合いで用いている。
そしてピアジェは、人間のシェマは、知識をインプット、つまり「覚える」だけでは形作られないと考えた。
知識は与えられたらそのまま習得されるわけではなく、最初はおぼろげな状態で存在する。
そしてその知識に合致するものに出くわしたときに初めて、「あれがこれか!」と言う風に理解する。
たとえばネコという概念を与えられた子供は、それだけではネコについて理解しない。
実際に猫に出会ったときに「これがネコというモノなのかな?」と思う。
これを「同化」と呼ぶ。
ただ、ネコにも色んな色の猫が居るし、種類も色々ある。
それらに出会う度に、頭の中で「コレもネコ、アレもネコなのか」と考え、ネコ以外の動物に触れる度に「コレはネコじゃない」「コレもネコじゃない」と考える。
コレによって、今まで持っていたネコの知識を変形する「調整」が行われる。
そうやってようやく「ネコというシェマ(自分なりの概念)」ができあがる。
こういう風に具体的にネコという生き物を見たり触ったりする経験が、ネコという概念を理解するのに役立つ。
そして勉強も同じように、具体的なモノに触れることによって、抽象的なモノへと理解が進む。
逆に言うと、具体的なモノに触れていない子供は、それについては理解できないと言うことになる。
勉強できる子供は、家の手伝いや雑用、工作やパズルなどの作業を通して具体的操作を身につけているからこそ、抽象的操作が行えるようになるわけで、それをすっ飛ばして先に進むことは出来ないのだ。