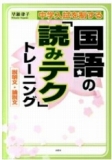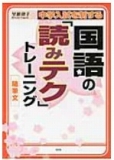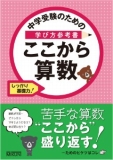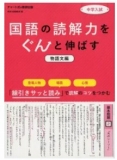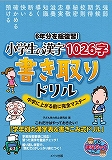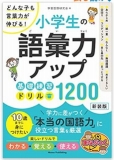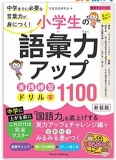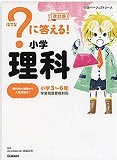6年生9月からの家庭学習をどうすべきか。
更新日:

受験生は、8月9月くらいから、入試本番に向けた勉強方法に切り替えることになるが、どういったことに焦点を当てるべきだろうか。
高校受験であれば、高校入試の内申点確保がまず第一だ。
そのために二学期あるいは前期末試験でしっかりした点数を取ることが重要で、それと並行する形で入試のための準備をする。
大学受験であれば、夏までに覚えた英単語や基本的な問題を復習しつつ、過去問などで重点的に勉強すべき単元を絞っていく。
そして中学受験の場合は、ただもうひたすら入試レベルの問題で点を取るための勉強になる。
中学入試は「取りやすい問題」と「取りにくい問題」があるので、取りやすい問題を確実に点数化するための勉強が重要だ。
基礎学力アップに
スポンサードリンク(楽天ブックス 広告)
中学受験の専門塾に毎日のように通わせている場合は、経験豊かな塾の方針に沿って塾の課題を優先してやった方が良い。
専門塾の場合、塾全体が受験に向けてカリキュラムを組んでいるはずだから、それに従えば良い。
塾の課題が多すぎてこなせないなら、やるべき課題とスルーする課題に切り分けて、子どもがパンクしないように気を使えば良い。
ただ問題は、週に2回か3回だけ塾に通わせていて、模試の成績も良くない場合だ。
こういった子どもの場合、塾任せにして丸投げしていると、成績はどんどん落ちていく。
というのも9月以降の模試は、入試を想定した全範囲の問題が出題されるからだ。
9月からの模試は、本当の実力が試される
9月以前の模試というのは、試験範囲が「最近学習した内容」が大前提で、変な話、対策して勉強しておれば、それなりの点数が取れた。
6年生の夏までの模試には、試験範囲をあらかじめハッキリと書いてある模試もあるし、範囲を示してない模試もある
大手中学受験チェーンの公開模試の場合などがそれで、たいてい範囲を示していなかったりする。
しかしそういう公開模試であっても、試験範囲は限定的である。
というのも範囲を公開していない模試であっても、その模試の主催塾がそれまでに学習している単元からしか出題されない。
教えていない単元から出題したら、その塾に通っている生徒が不利になるから、それは当然だ。
ある塾が公開模試をして、もしその塾に通っている生徒の成績や偏差値が外部からの受験生と比べて低かったら、面目が立たないしね。
最近学習したばっかり
→公開模試で良い点数が取れる
→この塾は信頼できる
→夏期講習をいっぱい申し込む。
…という流れになっている。
しかし9月以降の模試は、受験校を決めるための模試で、ほんとうの意味での「範囲なし全範囲」の模試になるし、他塾の生徒さんも学ぶべきことはすべて学んでいる状態で受験するわけだから、自塾の公開模試だからといって油断はできない。
狭い試験範囲では良い点数が取れていた子どもでも、範囲が広くなると解けない問題が多くなるので、今までのような点数は取れなくなる。
自塾で受験できるのは慣れてるし、若干は有利ではあるのだけど、それでもやはり偏差値は下がることが多い。
ではどうすればよいのか。
6年生の夏以降の家庭学習ミニ模試に
入試本番に向けて週に数回、短めの物語文と説明文、計算と一行問題(標準編)などを2周以上行い、問題があれば「文章題に強くなる」の単元で復習。それができたら発展編へ進むと良い。短めの問題だと子供も取り組みやすい。
楽天ブックス(広告)