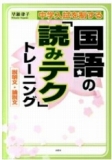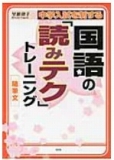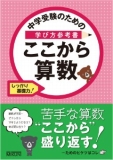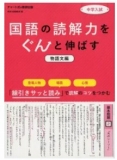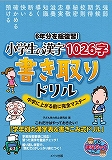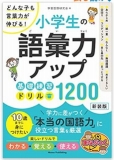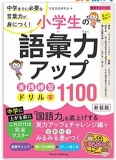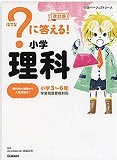9月からの模試は、いろんな塾の生徒が参加する
更新日:

6年生9月からの中学入試模試は、試験範囲が全範囲に広がるため、実力のない生徒は点が取れない。
夏までの模試は、範囲が限定されているため、その範囲だけしっかり別教しておれば、それなりに点数が取れる。
しかし9月以降の模試は、入試本番と同じ模試になるし、また模試を受験する子供の数も増えてくる。
そのため、通っている塾の模試であっても、なかなか良い成績は取れないし、成績をキープすることも難しい。
首都圏模試センターの6年生向けの模試は、中小の学習塾が参加する模試だが、9月以降は1000人くらいずつ受験生が増える。
大手専門塾の生徒さんたちも、腕試しに受験しに来るので、これは本当に難しい。
ではどうすればよいのか。、
基礎学力アップに
スポンサードリンク(楽天ブックス 広告)
9月からは、本番の試験と同じ形式で勉強する
6年生9月からの模試は、入試の試験範囲すべての範囲で行われる。
そのため、勉強法としては、入試本番と似た形で勉強すると良い。
具体的に書くと、国語・算数・理社の順で、毎日勉強する。
今日は国語、明日は算数、明後日は理科社会…というふうに日を分けて勉強すると、入試本番での切り替えができなくなる。
そうではなく毎回、入試の形式と同じような順番で学習するようにする。
入試は、国語・算数・理社という順番で行われるのがほとんどなので、勉強も、国語・算数・理社という順序で行うと良い。
それぞれ1時間ずつ学習するのが良いが、これは本番の入試が50分くらいだから、それに合わせる。
要するに、1時間経ったら科目が変わるというのが大事で、子どもにそういう感覚を身に付けさせる。
具体的にやることは、国語は漢字・語彙力のミニテスト、物語文の要約、説明文・随筆の要約問題くらいで、30分問題を解いて、30分見直すという感じ。
算数は計算問題と一行問題、そして少しむずかしい問題を順番にやる。
計算と一行問題のセットの問題集を20分やって、その後、特定の単元の問題を20分くらいやるというイメージ。
もちろん入試本番のように50分ずつやっても良いが、答え合わせややり直しもやらないといけないので、その時間を含めて一時間ずつという感じで良いと思う。
時間がなければ、問題数を減らしても良いが、順番は変えないことが肝要だ。
6年生の夏以降の家庭学習ミニ模試に
入試本番に向けて週に数回、短めの物語文と説明文、計算と一行問題(標準編)などを2周以上行い、問題があれば「文章題に強くなる」の単元で復習。それができたら発展編へ進むと良い。短めの問題だと子供も取り組みやすい。
楽天ブックス(広告)
毎日使える国語の読解問題集(楽天ブックス)
使える市販の問題集としては、次のような問題集がある。
漢字の問題集はいっぱいあるので、読解の問題集をいくつか挙げる。だいたい10分から20分くらいで解く問題が載っている。
問題文の長さは、前半が短めで、後半は長めなので、できれば複数の問題集を買って、冬までは前半の問題を中心にやると良いと思う。
これが入試に出る国語読解ベスト10
物語文の問題が10題、説明文の問題が10題の、計20題が載っている。問題文はちょっと長め。問題文はちょっと古めだけど、典型的な問題が集められている。
中学入試 実力突破 塾プラス国語長文
毎日使える算数のアラカルト問題集(楽天ブックス)
中学入試 実力突破 算数計算と一行問題【基本編】:偏差値55を超える
1日3題で60日分。計算問題2題と文章題1題。
前半の30日が偏差値50レベルで落とせない問題、後半が偏差値55で落とせない問題になっている。
見開きの左半分で2日分が載っているので、これを20分くらいでやればちょうどよい。
図形問題も載っているのが特に良い。計算と熟語も良いが、あちらは図形問題が殆ど載っていないし。
中学入試 実力突破 算数計算と一行問題【発展編】:偏差値63を超える
上の問題集より難易度が高めなので、基本編がほぼ完璧にできるような子供向け。偏差値50以下の中学を目指しているなら不要。
中学受験のための1日5題 まいにち算数: 90回でほんもの実践力
1日分が5題(計算3題+文章題+図形問題)で90日分のアラカルト問題集。ホップ・ステップ・ジャンプの3つのレベルになっているが、結構難しい。